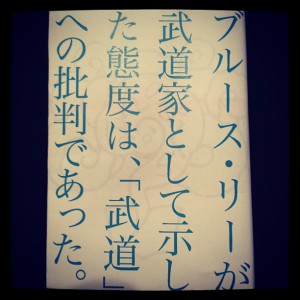新幹線が来るまでに時間があったので、ちょっと座って本を読めるような店を探した。ちょうどよさそうなオープンテラスの店を見つけた。しかし、カフェというよりレストランと呼んだ方がしっくりくる雰囲気の店だったので少し悩んだ。食事を頼まないといけないような気がしたからだ。おなかはへっていない。しかも店内では主婦たちが井戸端会議をしていて、落ち着いて本を読めそうでもない。でももう一度見るといつのまにか大勢いた主婦たちはいなくなっていた。それで店には誰もいなくなったので、僕はこの店に入り時間まで本を読むことにきめた。
コーヒー一杯でいすわるのもちょっと気がひけたので「デザートはありますか、アイスかなにか」と聞いたら「あります」というので席にすわった。提示されたメニューからイチゴ味のアイスを選択した。しかし同じ店員にそれを告げると「アイスはもう売り切れた」と言われてしまった。リンゴ味とメロン味についても同様に売り切れたそうだった。困ったことになった。
「でもさっき、アイスがあるって言ったじゃないですか」
「はい! メニューには用意してございます!」
「いや売り切れなんですよね」
「はい! 今日はもう売り切れです!」
若い女性の店員は終始ニッコニコしていて、全力で楽しく仕事をしている感があふれていた。「なんだか接客仕事に疲れたからこの客にちょっと意地悪でもしてうっぷんをはらしてやろう」とか、そういうふうではぜんぜんない。しかし僕は困っている。あなたのその素敵なモチベーションをもう少し効果的な方向へ活用してもらえないものだろうか。しかたない、コーヒーを頼もうと考えたが、ふと壁をみるととても大きな張り紙に「コーヒーだけのご利用はお断りしています」と書いてあった。いったい、さっきの主婦たちはどのようなメニューを注文してここに滞在する権利を獲得したのだろうか。全員でこのメニューの表紙にあるオススメのステーキセットを食べたのだろうか。おおぜいの主婦が丸テーブルを囲んで一斉にステーキを食べる風景を想像すると圧巻だった。
とにかく、僕はおなかが全然すいていないのだ。どうしようもないのでやはりこの店は出ようと考え、いったん下ろした腰をあげた。
「すいません、それじゃあやっぱり出ます」
「そうですか! それでは場所代1000円いただきます!」
「場所代?」
「はい! この店では、席にすわってからなにも注文しないで帰ると場所代が1000円かかるルールなんです! お客様はいま席にすわったので、ここから出るためには場所代がかかるのです!」
「しかし、僕はアイスがあると聞いたから入ったんです」
「アイスはメニューにあります!」
「でも売り切れなんでしょう」
「はい! どの味も大好評であっという間に売り切れました!」
「話が噛みあわねえや。とにかく払う気はありません。なんだったら警察を呼んでも……
あれ? もしかして、加藤さん?」
「え?」
「やっぱり! 小学校のときに同じクラスだった加藤さんだ!」
そこで目が覚めた。
 ファイナルファンタジー6をやりなおしている。
ファイナルファンタジー6をやりなおしている。